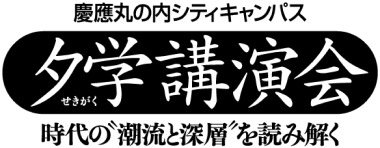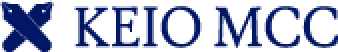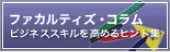講師紹介
このページを印刷

講演日 2013/07/12 (金)
小田嶋 隆
オダジマ タカシ
コラムニスト
講師略歴
1956年生まれ。東京・赤羽出身。早稲田大学卒業後、食品メーカーに入社。1年ほどで退社後、小学校事務員見習い、
ラジオ局ADなどを経てテクニカルライターとなり、現在はひきこもり系コラムニストと
して活躍中。
近著に『人はなぜ学歴にこだわるのか』(光文社知恵の森文庫)、『イン・ヒズ・オウン・
サイト』(朝日新聞社)、『9条どうでしょう』(共著、毎日新聞社)、『テレビ標本箱』(中公
新書ラクレ)、『サッカーの上の雲』(駒草出版)、『1984年のビーンボール』(駒草出版)、
『小田嶋隆のコラム道』(ミシマ社)、『地雷を踏む勇気』『もっと地雷を踏む勇気』(技術
評論社)などがある。
「新潮45」「サイゾー」「サッカー批評」「WEBスポルティーバ」「日経ビジネスオンライン」
などでコラムを連載中。
2012年4月より、TBSラジオ「たまむすび」水曜日コメンテーター、
テレビ朝日・朝日ニュースター「ニュースの深層」木曜日キャスターを担当。
講演内容
「コラムという生き方」当日は、コラムニストという「限定された位置」から世界を見渡す際の視点の置き方
と、「コラム」という「定められた枠組み」の中に主題を落とし込んでいくための技巧に
ついてお話しするつもりです。
修辞上の技巧の問題から出発して、困難な時代を生きるヒントをご提供できればと
思っています。
■ この講演にご関心をお持ちの方へ ― 夕学スタッフからおすすめの3講演 ―
・4/24(水) 橘玲氏 「「日本国破産」の資産運用戦略」
・6/20(木) 古市憲寿氏 「起業の社会学」
・7/16(火) 萱野稔人氏 「縮小社会の文明論」
主要著書
『我が心はICにあらず』BNN、1988年(1989年・光文社文庫)『安全太郎の夜』河出書房新社、1991年
『笑っておぼえるコンピュータ事典』ジャストシステム 、1992年
『パソコンゲーマーは眠らない』朝日新聞社、1992年(1995年・朝日文庫)
『山手線膝栗毛』ジャストシステム、1993年
『仏の顔もサンドバッグ』宝島社、1993年
『コンピュータ妄語録』ジャストシステム、1994年
『「ふへ」の国から—ことばの解体新書』徳間書店(新書)、1994年
『無資本主義商品論-金満大国の貧しきココロ』翔泳社、1995年
『罵詈罵詈―11人の説教強盗へ』洋泉社、1995年
『DOGZ パソコンに住んだ犬』ビー・エヌ・エヌ新社、1997年
『日本問題外論―いかにして私はデジタル中年になったか』朝日新聞社、1998年
『パソコンは猿仕事』小学館(小学館文庫)、1999年
『人はなぜ学歴にこだわるのか』メディアワークス、2000年(2005年・智恵の森文庫)
『かくかく私価時価—無資本主義商品論1997‐2003』ビー・エヌ・エヌ新社、2003年
『イン・ヒズ・オウン・サイト』朝日新聞社、2005年
『テレビ標本箱』中央公論新社(中公新書ラクレ)、2006年
『サッカーの上の雲』駒草出版、2007年
『1984年のビーンボール』駒草出版、2007年
『テレビ救急箱』中央公論新社(中公新書ラクレ)、2008年
『人生2割がちょうどいい』(共著)、講談社、2009年
『ガラパゴスでいいじゃない』(共著)、講談社、2010年
『その「正義」があぶない。』日経BP社、2011年
『地雷を踏む勇気 人生のとるにたらない警句』技術評論社、2011年
『いつだって僕たちは途上にいる』(共著)、講談社、2012年
『小田嶋隆のコラム道』ミシマ社、2012年
『もっと地雷を踏む勇気 わが炎上の日々』技術評論社、2012年
『場末の文体論』日経BPマーケティング、2013年
このページを印刷